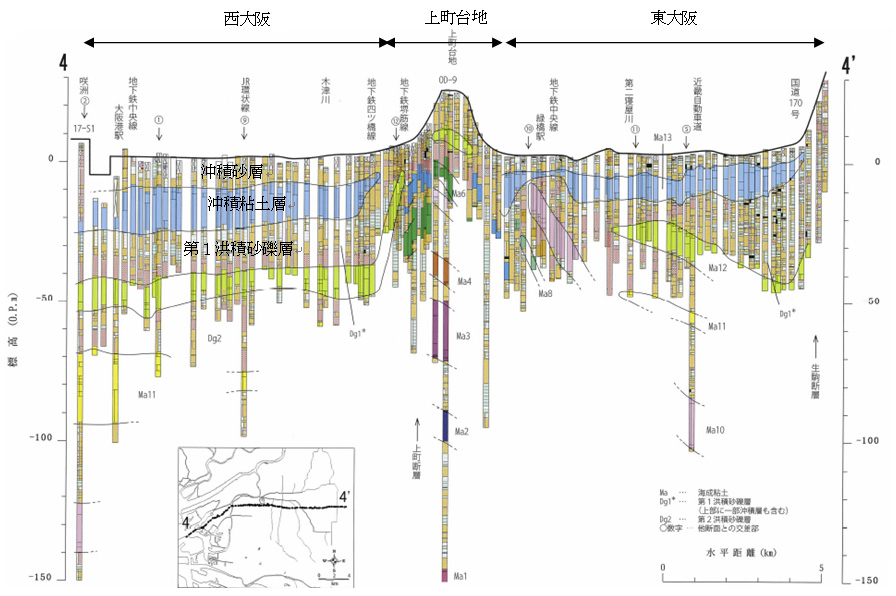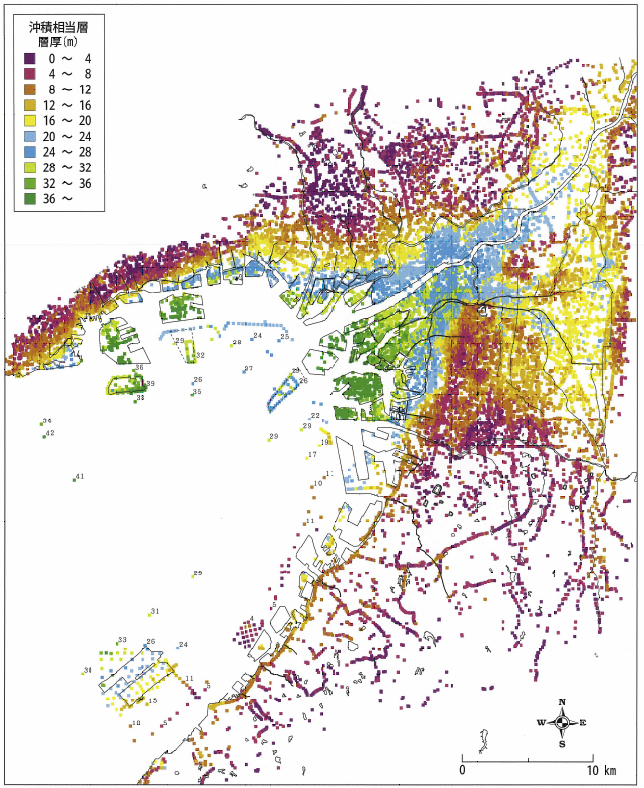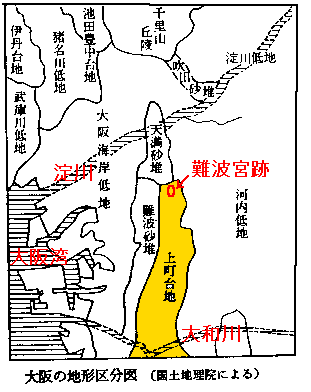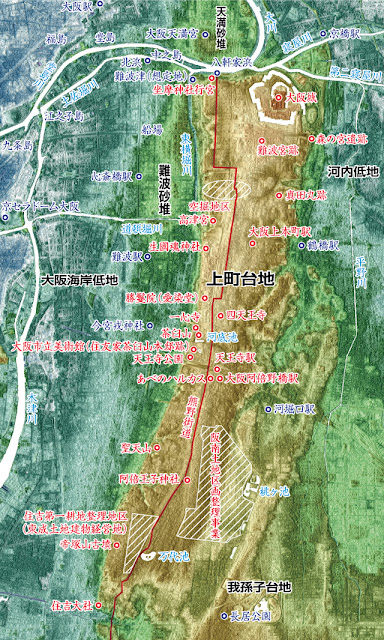<1> 周知の事実に属するが、台湾における最初の図書館は、1901年(明治34年)1月27日に開館した私立台湾文庫である。この私設図書館は台北市書院街淡水館内に設立された(註1)。その後、運営資金の枯渇から、まもなく私立台湾文庫は休館状態になったが、1914年(大正3年)9月14日、台湾総督府は台湾総督府図書館令を発布して台湾総督府図書館を開設し、そこに私立台湾文庫所蔵の蔵書を吸収した(註2)。その後、台湾全土に公私立図書館が開設され、1932年(昭和12年)にはその総数は83館に及んだ(註3)。
日本統治期台湾において、勅令31号を以て、台北帝国大学が開設されたのは1928年(昭和3年)である(註4)。それまで日本国内にあった東京・京都・東北・九州・北海道帝国大学についで、日本政府は朝鮮半島と台湾の二地域に、京城帝国大学(1926年開学)と台北帝国大学の、いわゆる「外地型帝国大学」の開学を許可した。これらの直接的な運営主体は、それぞれ朝鮮総督府と台湾総督府であったが(註5)、日本政府の帝国大学設置令(1919・大正8年2月制定、勅令第12号)に基づいて設置されたことは言うまでもない。
したがって台北帝国大学に対して、台湾総督府が植民地統治の威信をかけて、膨大な教育投資をおこなった。それに関する公式発表はないものの、新聞報道によると、111万7千余円に達したという(註6)。その初期投資の大半は、キャンパス購入費と校舎など建設費、教授及び職員招聘費などであったにちがいないが、その中に附属図書館開館費も含まれていた。我々の関心に従って、次に、台北帝国大学附属図書館に関する沿革を時系列で説明する。
1,1928年3月25日:台湾総督府構内にあった台北帝国大学事務室を台北高等農林学校内に移転(付属図書館事務室も含む)。
2,1928年6月15日:台北帝国大学附属図書館規定を制定
3,同日:台北帝国大学附属図書館閲覧規則を制定
4,1929年4月19日:文政学部本館竣功により付属図書館を文政学部本館に移転
5,1930年1月19日:付属図書館竣功により同事務室及び閲覧室を移転。
6,1931年9月10日:付属図書館書庫及び閲覧室竣功。
・図書館本館 2階建て煉瓦造 1棟 295,30坪
・図書館書庫及び閲覧室 2階建て鉄筋造 443坪
・倉庫及び荷解室 2階建て煉瓦造り 43.75坪
言うまでもなく帝国大学の慣習によって、各学部各講座教室にも関連図書・研究資料が備置されたので、1928年開学時から1945年8月15日までの閉校時までに購入・蒐集・寄付された図書の冊数は、諸事情によって正確に把握できない。戦時体制下にあって、敗戦の1945年に至ると、台北帝国大学による公式発表が残されていないこともあり、その上に戦後の混乱もその理由の有力な一つである。
しかしながら、1945年11月15日に台北帝国大学が中国の国民政府代表の羅宗洛(当時、中央研究院植物学研究所所長)らによって接収されたとき、
「接収時拠原有記載本館書籍数475000冊、其中10000冊蔵於本館書庫、其余分置各学院及各講座中、此外拠原載所知士林預科直有蔵書11674冊。」(『国立台湾大学概況』中華民国36年4月、95頁)
とあることによって、概略は把握できる。(註7)。
<2>台北帝国大学図書館はその威信をかけて、日本内地の各帝国大学に比べて遜色のない質と量の蔵書を誇る図書館を建設したいと願った。わずか16年間の命脈しかなかった台北帝国大学であったが、その間に約48万冊の図書を購入・集書したとは驚きである。1年で平均3万冊である。しかしながら、たとえ潤沢な図書購入費があったとはいえ、帝国大学附属図書館であるだけに、その基本方針は「豪華な1点買い」とは無縁であった。むしろ台湾大学図書館に残された図書を見る限り、台北帝国大学の直前に設立された九州大学法文学部(1924年設立)の蔵書構成と酷似していることを考え合わせると、主に教育用基本図書購入に力点を置いた集書方針が立てられた上で、その基本図書購入リストを作成するに当たって帝国大学図書館間の情報交換があったと推定してもよいだろう。
上記したように、台北帝国大学附属図書館が新設されたとき、ほぼ同一時期に、1924年に九州帝国大学法文学部が、加えて1926年に京城帝国大学が開設されたために、3帝国大学は競って図書充実に努めることになった。しかも慶応大学や早稲田大学などの私立大学も図書蒐集レースに加わった(註8)。昭和の初期には、まだ各種文庫を購入するに幸せな時代であった。
台北帝国大学附属図書館に所蔵された国文学関係個人文庫の桃木文庫や長沢文庫に関しては、中野三敏教授の紹介に譲り、ここではそれ以外の個人文庫を掲載したい。
(1)人文学関係
(掲載順:(『国立台湾大学概況』中華民国36年4月、95~97頁)
①藤田文庫:346部、506冊:昭和4年3月21日購入。故文学博士藤田豊八旧蔵。東洋史関係の洋書。主にシナ海や南海交通に関する文献。因みに藤田博士旧蔵の漢籍1700部余、21600冊余りは東洋文庫に寄贈された。(註9)
②深田文庫:1315部、1988冊
③Huart文庫:932部、2275冊:昭和4年1月19日購入。故Clement Huart氏旧蔵。元L’Ecole des Langues Orienta les Viviantcs教授。フランスアカディミア会員。アラビア・ペルシャ・トルコなどの諸国を中心とした言語学関係・歴史・地理・紀行・風俗習慣などの資料(註10)
④久保文庫:894部、7437冊
⑤桃木文庫:540部、4879冊(註11)
⑥長沢文庫:505部、1627冊
⑦大鳥文庫:829部、1750冊:昭和4年3月21日購入、故男爵大鳥富士太郎氏旧蔵。東西交通史関係書洋書が多い。またキリスト教関係の古版本や貴重書も少なくない(註12)
⑧坂口文庫:601部、1345冊:昭和3年10月29日購入。故文学博士坂口昴氏旧蔵。西洋史関係の洋書と一般関係の和書で構成(註13)。
⑨烏石山房文庫:12099部、34803冊:昭和4年1月25日購入。烏石山房旧蔵。福州の名家の旧蔵にして、乾隆時代龍景翰蒐集し、其の後一次散亡したが、同治時代龍易圖再び蒐集して、烏山麓に収蔵したもので、経史子集にわたって良く網羅されている(註14)。
⑩Shiller文庫:部数・冊数共に未詳
(2)自然科学関係
⑪Molisch文庫:8349部、8669冊
⑫田代文庫:257部、441冊
⑬渡瀬文庫:316部、306冊
⑭青木文庫:部数、冊数共に未詳
⑮田中文庫:2225部、3069冊(註15)。故田中長三郎教授旧蔵。台北帝国大学附属図書館初代館長。
ところで、今日的観点から見れば、当時にあってそれほどの高い価値が認定されていなかったももの、現在ではその希少価値ゆえに、台湾大学の至宝となっている資料がある。
⑯伊能嘉矩文庫:台湾少数民族関係資料137種、約300点(註16)。
⑰旧台北帝国大学土俗人種学標本室収蔵品:1905種、約2500点の「台湾原住民の土俗品」(註17)。
⑱沖縄関係史料:小葉田淳によって蒐集された『歴代宝案』249冊(第1集42冊、第2集187冊、第3集13冊、別集3冊、目録4冊)や『氏集』1冊(琉球王府の系図座に保管されていた家譜目録。総家譜数約2800余り)、『親見世日記』6冊など
⑲オランダ・ハーグ国立文書館所蔵台湾関係公文書写真原板:25、222枚。(註18)
⑳上田文庫:「331部、4622円/登録番号 156321~156651 国文研究室」
(註19)。東京帝国大学教授上田万年氏旧蔵書。洒落本約80点、黄表紙約200点の近世文学コレクション。
などが、それである。
また、その全貌は不明であるが、台北帝国大学開学記念展覧会に展示された史学科資料群に、注目すべき逸品がある。例えば1935年には、
「北条実政自筆書状、足利義満御教書、北条氏輝下知状、~~(中略)~~法華経義疏・蒙古襲来絵詞・物語絵巻等の図巻及び武鑑~~(中略)~~末吉船の図、茶屋新六交趾貿易の絵巻――」(『台北帝国大学史学科研究年報』第2輯、1935年、422-423頁)
を展示し、さらに1936年には、
「院応牒、北条実政自筆書状、感神院所司奉状を始め古文書31点、沖縄県古碑拓本7点、法隆寺百万陀羅尼、古筆手鑑、土佐光起筆三條西実隆画像を始め標本7点、~~(中略)~~暹羅行御朱印状、暹羅国書、歴代宝案等8点、参考品に大阪城の図、ゼーランジャ城図を、更に暹羅関係欧文史籍63点」(『台北帝国大学史学科研究年報』第3輯、1936年、377頁)
などが展示された。これに加えて、台湾大学図書館には、
「35年3至12月間、日人陸続遺回、本館曾収購日員私人蔵書七千余冊、其中頗有美本」
(『国立台湾大学概況』中華民国36年4月、95頁)
が収まったという。つまり敗戦後、日本への引揚に際して、台北の自宅や大学研究室など
に個人蔵書を残してきた教授陣の中には、井原西鶴などの江戸文学関係者を集書した滝田
貞治(日本文学)・上田文庫などのコレクション形成に努力した安藤正次(日本語学)、『歴
代宝案』などの琉球関係資料を精力的に収集した小葉田淳(日本史学)・解剖学で著名な金
関丈夫などの「目利き」に枚挙がない。
ところで、台北帝国大学附属図書館では、その各書籍の登録日時から分かるように、戦火激しい1943年秋に至って、「内地」の諸大学では購入さえ出来なくなったときでも、「外地」にあった台北帝国大学では次々と貴重書を購入していた。次第に連合国軍によってアジアの海上制海権も押さえられ、有力な港には機雷が設置され始めて、自由に航海できない状態であった。しかも日本から台湾への定期船も途絶えがちであったにもかかわらず、東京の反町弘文荘・一誠堂・厳松堂らの著名な古書店の有力な販売先が、台北帝国大学附属図書館であったし、京城帝国大学・満州国建国大学であった。
こうしてクオリティーの高い典籍集積地が台北に出現した。
<3>ところで1945年以降、これら日本統治期に設立された二つの帝国大学に保存された日本語古典籍資料情報紹介を、熱心に取り組んだのが、金子和正氏・鳥居フミ子氏と須田悦生氏であった。三人による旧台湾大学研究図書館所蔵本(現台湾大学総図書館特蔵室蔵本)調査結果は、多くの日本文学研究者を驚かした。改めて三氏の労苦に感謝し、その偉業を賞賛したい。
<5>1998年に台湾大学総図書館が新築されたことを契機にして、呉明徳館長(当時)の英断と、夏麗月主任と洪淑分係長の適切な指導で、それまで台湾大学全体に分散されて架蔵されていた「和本」の集中化が義務づけられたことによって、1万冊以上の和本が新たに発見されることとなった。同館6階の書庫に仮収蔵されていたこれらの典籍の山を目の前にしたときの感激と驚きを、私は今も忘れない。
これらの新規収蔵本は台湾大学文学院・理学部・農学院・医学院・法学院などの学部図書館・各研究室や人類学系図書館から、総図書館に搬入されたという。それまで旧台湾大学研究図書館において管理・保管されてきた上田文庫や長沢文庫などとは異なり、これらの本は激しい虫食い状態にあった上に、また高温多湿の中で充分な管理がなされなかったために、本の形態をとどめず板状になってしまっている本も少なからずあった。1945年以降、これらの図書利用者が皆無に近かったために、どうしても管理が等閑になりがちであったにちがいない。特に変体仮名で刊行された俳諧や江戸の小説類は、台湾の方々に読解も困難であったし、それまでの対日感情も作用して不要不急の図書への配慮は十分ではなかったようである。
<5>台湾大学総図書館において、和本が一カ所で集中管理保存されることになり、しかも大学内の各機関別に独自に附けられた分類番号の不都合さを顧みて、あらたに特蔵室独自に厳密に「通し番号」をつける作業が貫徹された。こうした日本古典籍に関する基本方針が立てられたことによって、それまでの配架番号が全面的に改められた。
幸いであったのは、その「通し番号」作業が完了していたために、2000年度に中野三敏九州大学名誉教授を団長とした九州大学調査チームが訪台し、台湾大学総図書館徳蔵室所蔵日本語古典籍の悉皆調査に着手した時にも、大きな混乱は発生しなかった。それ以降、今年度に至るまでの調査記録は、別掲したとおりである。調査人員は延べ人数約??名、総滞在日数は約???日を要した。
九州大学チームによる書誌調査結果が進展した結果、同大学所蔵日本語古典籍のほぼ全体を調査し終えたことは、僥倖であった。
我々が展開した調査結果によると、旧台北帝国大学本・現台湾大学総図書館特蔵室所蔵の和本総数は、約2万2千冊に及ぶと判明した。この2万2千冊の和本は、なるほど台湾特有の高温・多湿な気候の中に放置された時期を経たために、破損や劣化が進んでおり、早急な保存策を講ずる必要のあるものも少なくない。例えば井原西鶴の諸作などは、その典型である。
管見に入った限り、今日まで、旧日本統治地域所在各種図書館所蔵和本に関する悉皆調査をした資料情報は、朝鮮半島に関しては釜山広域市図書館所蔵本、韓国国立中央図書館所蔵本、ソウル大学校中央図書館所蔵本、大邱市立図書館の3館、中国東北部に関しては遼寧省立図書館所蔵本の1館に過ぎない。それゆえに、台湾大学総図書館所蔵本の悉皆調査は6番目に当たるはずである。
<6>我々の関心に従えば、和本のみならず、漢籍室に所蔵されている漢籍和刻本の書誌的調査も希望するが、台湾大学総図書館の諸事情によって、我々が直接書誌的調査を実施できない状態にあり、やむなくリストで確認せざるをえない。それでも現在までに次の2冊が刊行されているので、大略は把握できる。
『國立臺灣大學普通本線装書目』 國立臺灣大學圖書館編、1971年
『国立台湾大学普通本線装書目』(補編、索引)国立台湾大学図書館編、1978年
この漢籍目録中の和刻本取り出し作業は未だ実施していないものの、一見すると約2000冊の漢籍和刻本所蔵を予測させる。将来の課題として残しておきたい。
(7)本研究は以上のとおりであるが、それだけに我々の研究目的の一つである、台湾に設立された各種図書館所蔵残置本の現状把握に努めると共に、所蔵者の意向を十分に尊重しつつ、永く伝来させるための整理保存修理の方策を立てることも、我々の責務であると信じる。
過去の歴史的経緯からしても、また台湾国内の世論は、日本語古典籍の整理よりも、まず自国の古典籍を先に整理・保存すべきであると主張している。本の価値にしても、またその活用度の高さからしても、それは当然な論理であるが、それでも貴重な日本語古典籍が放置され続けて良いはずはない。
それゆえに日本国外にあるだけに十分に所蔵者の意向を尊重しつつ、台湾大学総図書館が架蔵する日本語古典籍―主に明治以前―の書誌学的調査を実施し、およそ50数年間、どのような架蔵状況にあるかを、まず調査し、それを元にしたマイクロフィルムを作成し、もしくは画像の電子化、及びデータ・ベース作成などを通して、インターネットによって国内外に情報公開することで、これまでよりも遙かに大量な文献所在情報データベースを構築することが、我々の課題となるはずである。
(註1)開館するに当たり集書された印刷物は、和漢書5639冊、洋書224冊、総計5863冊であった。
(註2)台湾教育会編『台湾教育沿革史』、1934年〈昭和14年〉、1093-1095頁)
(註3)蔵書総数は、約35万3千冊。台湾教育会編『台湾教育沿革史』、1934年、1093頁)。
(註4)大学の沿革は、以下の通りである。
1,1938年3月17日:勅令32号及び33号によって、文政学部4学科7講座及び理農学部4学科6講座の2学部が設置された。
2,1938年12月27日:勅令287号によって、文政学部4講座、理農学部9講座を増設。
3,1929年4月11日:勅令60号令によって、文政学部に4講座、理農学部に1講座を増設。
4,1930年2月27日:勅令32号によって、文政学部に4講座、理農学部に4講座を増設。
5,1935年12月26日:勅令318号および319号によって、医学部7講座を新設。1936年1月1日より施行。
6,1937年8月9日:勅令409号によって、文政学部に1講座、理農学部に2講座増設。
7,1938年1月12日:勅令28号によって、医学部に8講座を増設。
8,1941年4月5日:勅令390号によって、理農学部に1講座を増設。
9,1941年4月5日:勅令291号によって、工学部を新設。1943年1月1日より施行。
10,1943年3月31日:勅令298号によって、理農学部を理学部と農学部に分離。
11,1943年3月31日:勅令299号によって、理学部12講座、農学部19講座、工学部16講座と定める。
また、『臺灣大學設立論』久保島天麗編、臺灣大學期成同盟会、1920年を参照のこと。
(註5)昭和3年3月制定の勅令30号「台北帝国大学に関しては帝国大学令に依るの件」
本文「台北帝国大学に関しては帝国大学令に依る但し同令中文部大臣の職務は台北総督之を行ふ」
(註6)「濫費的台湾大学」『台湾民報』第252号、1929年3月17日付け。(呉密察ほか「植民地大学とその戦後」『記憶する台湾』東大出版会、2005年332頁)
(註7)『書和人』「国立台湾大学図書館之発展及蔵書状況」
(註8)例えば、慶応大学は1930年に「小山内薫旧蔵、洋四千冊、和漢二千冊、計六千冊」を購入した(「慶應義塾図書館史」1972年1月
http://www.mita.lib.keio.ac.jp/history/history.html)
(註9)『台北帝国大学文政学部 史学科研究年報』第1輯、1934年、460頁
(註10)『台北帝国大学文政学部 史学科研究年報』第1輯、1934年、460頁、および、”atalogue de la bibliotbeque de feu Clement Huart” Bibliograohia
Taihokuna
No1,( Taihoku
Imperial University Library,1930)
(註11)台北帝国大学附属図書館の図書購入台帳には、
「桃木文庫 540部 4879冊
本邦古典ノ蒐集ニシテ古写本古版本多ク、殊ニ日本書紀ノ写本、異版ノ珍本多シ、桃木武平翁ノ旧蔵ニシテ曾テ京都帝国大学ニ依託保管シアリシモノ」
(鳥居フミ子『近世芸能の発掘』勉誠社、1995年、76頁)
とあり、台湾大学図書館接収時の冊数と異なっている。
(註12)『台北帝国大学文政学部 史学科研究年報』第1輯、1934年、460頁
(註13)『台北帝国大学文政学部 史学科研究年報』第1輯、1934年、460頁
(註14)『台北帝国大学文政学部 史学科研究年報』第1輯、1934年、460頁
(註15)『台湾大学図書館田中文庫目録』台湾大学図書館、1998年。
(註16)胡家愉・崔伊蘭編『台大人類学系蔵伊能蔵品研究』国立台湾大学出版中心、1998年および、国立台湾大学図書館編『伊能嘉矩與台湾研究特展専刊』台湾大学図書館、1998年参照。
(註17)呉密察ほか「植民地大学とその戦後」『記憶する台湾』東大出版会、2005年310頁
(註18)移川子之蔵「和蘭ハーグ国立文書館所蔵台湾関係文書目録」『台北帝国大学文政学部史学科研究年報』第5輯、1938年
(註19)鳥居フミ子『近世芸能の発掘』勉誠社、1995年、100頁。鳥居氏の見聞によると、1983年頃に、台湾大学図書館に於いて、上田文庫の原表紙を除去して、「卵黄色の替表紙」に取り替え作業中であったそうである。
(註20)なお台湾に関しては、国家図書館台湾分館所蔵本が宮崎修多氏によって整理されたと聞く。
加えて、台北帝国大学の昭和3年から昭和8年の教官と文政学部在籍学生の総数の推移は次の通りであり、
|
年度 |
教官 |
学生 |
教官一人あたり の学生数 |
|
1928年(昭和3年) |
25 |
23 |
0.9 |
|
1929年(昭和4年) |
37 |
59 |
1.6 |
|
1930年(昭和5年) |
42 |
92 |
2.2 |
|
1931年(昭和6年) |
45 |
96 |
2.1 |
|
1932年(昭和7年) |
43 |
82 |
1.9 |
|
1933年(昭和8年) |
45 |
70 |
1.3 |
(出典:各年度の『台北帝国大学通報』)
この学生の大半は文政学部法学科所属であり、文学科や史学科所属の学生は毎年5名内外であった。文政学部所属の教官は、以下のメンバーであった。
|
講座名 教官名 |
講座名 教官名 |
|
東洋史学 青山公亮 言語 浅井恵倫 西洋哲学 淡野安太郎 教育学 伊藤猷典 経済学 今西庄次郎 東洋哲学 今村完道 南洋史学 岩生成一 刑法学 植松正 国文学 植松安 土俗学・人種学 移川子之蔵 哲学 岡野留治朗 東洋文学 神田喜一郎 経済学 楠井隆三 東洋史学 桑田六郎 英文学 工美??? 東洋哲学 後藤俊瑞 財政学 木幡清金 国史学 小葉田淳 シナ学 徐征 西洋史学 菅原憲 東洋倫理学 世良寿男 行政学 薗部敏 |
国文学 瀧田貞治 倫理学 田中熙 法律学 中井淳 商法学 中川正 国史学 中村喜代三 憲法学 中村哲 経済学史 東嘉生 教育学 福島重一 国語学 福田良輔 心理学 藤沢仲 民法 宮崎考治朗 南洋史学 箭内健次 西洋文学 矢野禾積 農業政策 吉武昌男 心理学 力丸慈円 |
|
南洋史学 藤田豊八 昭和3年~昭和4年 哲学 務台理作 昭和3年~昭和10年 南洋史学 村上直次郎 昭和3年~昭和10年 国語学 安藤正次 昭和3年~昭和10年 哲学 柳田謙十郎 昭和4年~昭和16年 |