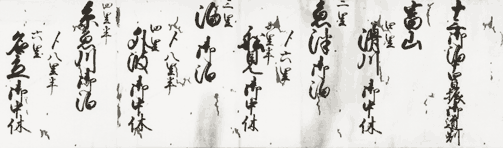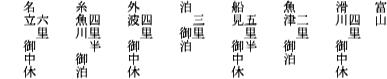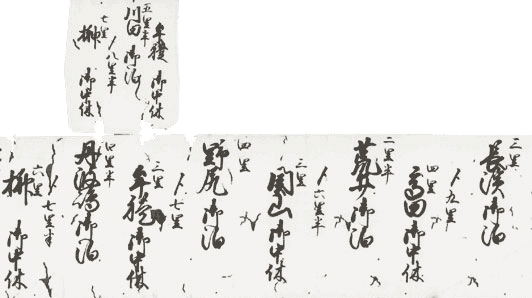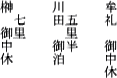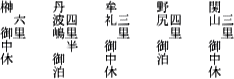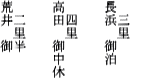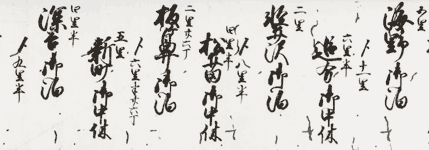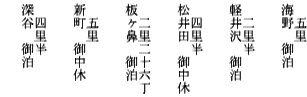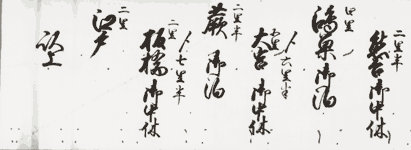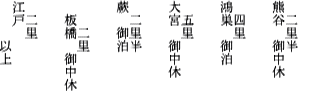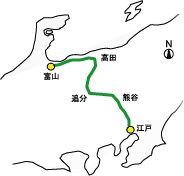*日本で鷹狩を愛した三大人物は、桓武天皇・信長・家康
織田信長や徳川家康の二人は有名であるので、後日に紹介することとしたいが、天皇に拝謁するに、鷹狩姿で出向いた信長は気にいっている。
さて、桓武天皇。長岡京および平安京への遷都で有名な桓武天皇だが、意外と知られていないのが、天皇の鷹狩好き。
記録に残る桓武天皇の鷹狩は全128回に達するという(鈴木拓也『蝦夷と東北戦争』吉川弘文館、2008年、144頁)。例えば、次の記事である。
『『続日本紀』延暦2年
とある、この「交野」とは大阪府枚方市・交野市付近。日本古代の鷹狩の様式を知らないだけに、博雅の士のご教示を得たい。
なお、我が九州大学に鷹狩を研究するcommitteeがあり、
丸山大・著「 大韓国調査報告」があることを紹介しておきたい。なお、朝鮮通信使一行の鷹狩に言及してほしかったとは、欲張りであろうか。
hhe-news5.pdf (kyushu-u.ac.jp)
日本列島における鷹・鷹場と環境に関する総合的研究
研究課題
| 研究課題/領域番号 | 16H01946 |
|---|---|
| 研究種目 | |
| 配分区分 | 補助金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 研究分野 | 日本史 |
| 研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 | 福田 千鶴 九州大学, 基幹教育院, 教授 (10260001) |
| 研究分担者 | 大賀 郁夫 宮崎公立大学, 人文学部, 教授 (00275463) 籠橋 俊光 東北大学, 文学研究科, 准教授 (00312520) 東 昇 京都府立大学, 文学部, 准教授 (00416562) 久井 貴世 北海道大学, 文学研究院, 准教授 (00779275) 東 幸代 滋賀県立大学, 人間文化学部, 教授 (10315921) 森田 喜久男 淑徳大学, 人文学部, 教授 (10742132) 渡部 浩二 新潟県立歴史博物館, その他部局等, 研究員 (20373475) 伊藤 昭弘 佐賀大学, 地域学歴史文化研究センター, 教授 (20423494) 堀田 幸義 宮城教育大学, 教育学部, 教授 (20436182) 江藤 彰彦 久留米大学, 経済学部, 教授 (30140635) 兼平 賢治 東海大学, 文学部, 准教授 (30626742) 安田 章人 九州大学, 基幹教育院, 准教授 (40570370) 水野 裕史 筑波大学, 芸術系, 助教 (50617024) 武井 弘一 琉球大学, 国際地域創造学部, 准教授 (60533198) 相馬 拓也 京都大学, 白眉センター, 特定准教授 (60779114) 中澤 克昭 上智大学, 文学部, 教授 (70332020) 岩淵 令治 学習院女子大学, 国際文化交流学部, 教授 (90300681) 藤實 久美子 国文学研究資料館, 研究部, 教授 (90337907) 大坪 舞 佐世保工業高等専門学校, 基幹教育科, 講師 (00781098) 荻 慎一郎 高知大学, 教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門, 教授 (60143070) |
| 研究期間 (年度) | 2016-04-01 – 2021-03-31 |
| 研究課題ステータス | 完了 (2020年度) |
| 配分額 *注記 | 44,330千円 (直接経費: 34,100千円、間接経費: 10,230千円)2020年度: 6,110千円 (直接経費: 4,700千円、間接経費: 1,410千円)2019年度: 10,140千円 (直接経費: 7,800千円、間接経費: 2,340千円) 2018年度: 8,970千円 (直接経費: 6,900千円、間接経費: 2,070千円) 2017年度: 10,140千円 (直接経費: 7,800千円、間接経費: 2,340千円) 2016年度: 8,970千円 (直接経費: 6,900千円、間接経費: 2,070千円) |
| キーワード | 鷹 / 鷹狩 / 鷹場 / 環境 / 生態系 / 狩猟 / 鷹書 / 鷹狩図 / 環境史 / 日本史 / 鷹場(狩場・猟場)) / 鷹狩文化 / 鷹場(猟場・禁漁区) / 鶴 / 鴨堀 / 日本列島 / 鷹狩美術 / 鷹場(狩場・猟場) / 鷹場(御猟場) |
| 研究成果の概要 | 日本列島上において、鷹と人間は長い共生の歴史を歩んできた。また、5世紀の古墳時代から江戸幕府瓦解の19世紀後半に至るまで、鷹狩は権力と深く結び付きながら、連綿と続けられてきた。そこには、日本の風土や社会のなかで地域・時代・階層、あるいは狩猟の目的等にあわせて独自に発展してきた固有の歴史が存在する。本研究課題では、それらの通史的な展開を検討するとともに、近世になって全国的に設置された鷹場が環境に与えた影響やそこでの人々の生活について検討し、この二次環境としての鷹場が幕末に失われることで、近代化過程における環境破壊や生態系の変化といった問題が引き起こされるという重要な意義を問題提起した。 |
| 研究成果の学術的意義や社会的意義 | 本研究では、日本史を貫く重要な要素でありながら等閑視されてきた鷹狩の歴史を紐解き、自然界のタカが人間によって鷹という人為的存在となり、犬や馬とともに人間と長く共生してきた道程を日本列島上にフィールドを限定して解明した。とくに江戸時代に全国的に設置された鷹場が自然環境に与えた影響の大きさや中世から近世にかけて、鷹が鷂・隼から大鷹へと変化し、獲物も雉から鶴へと変化する意義などを新たに解明した。 |